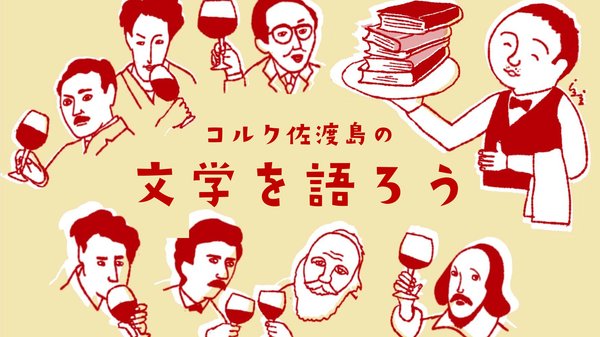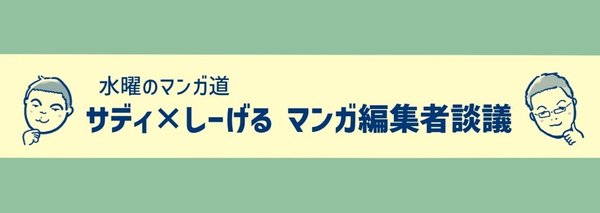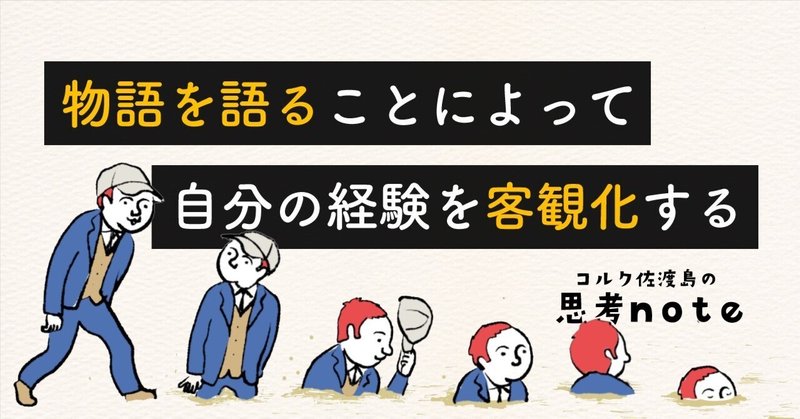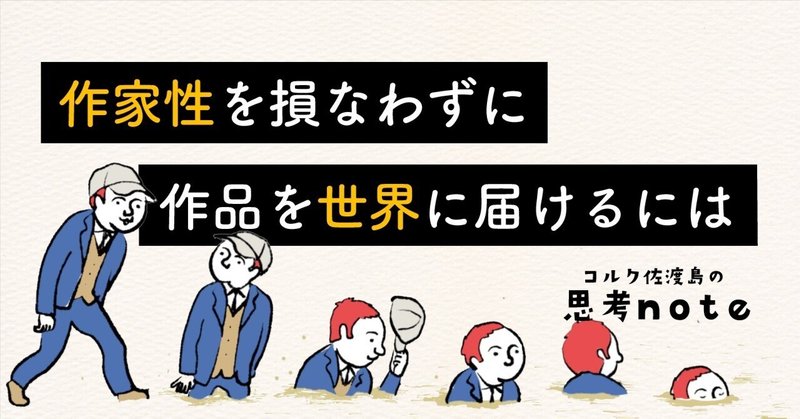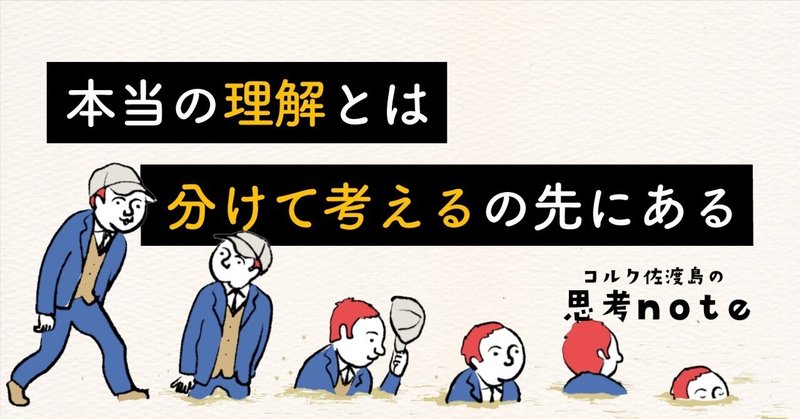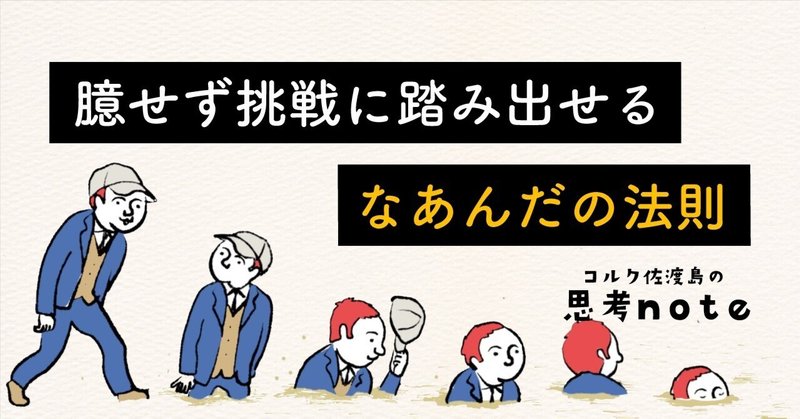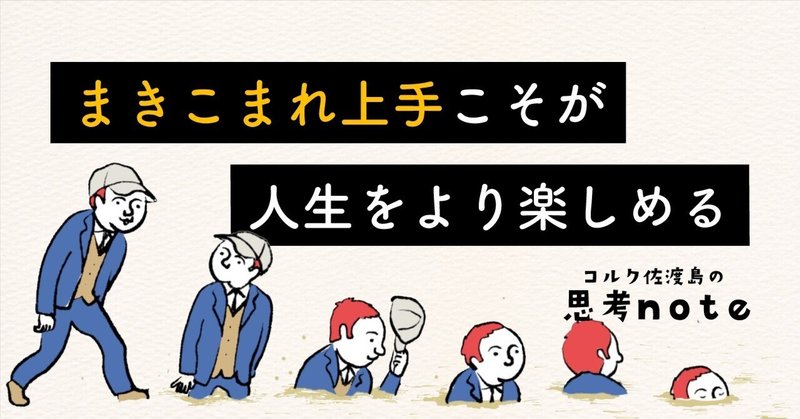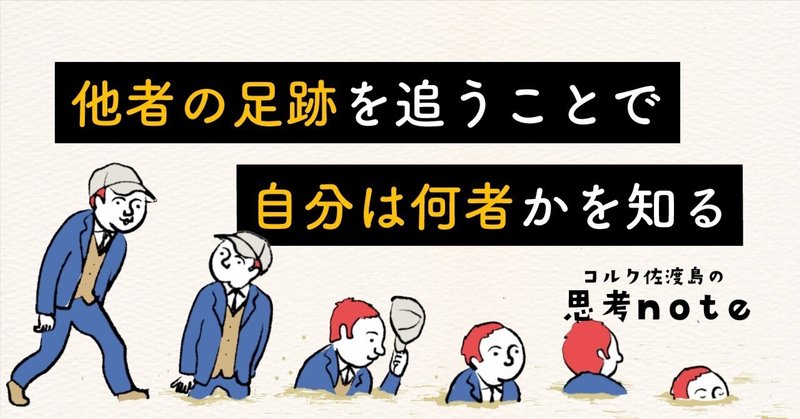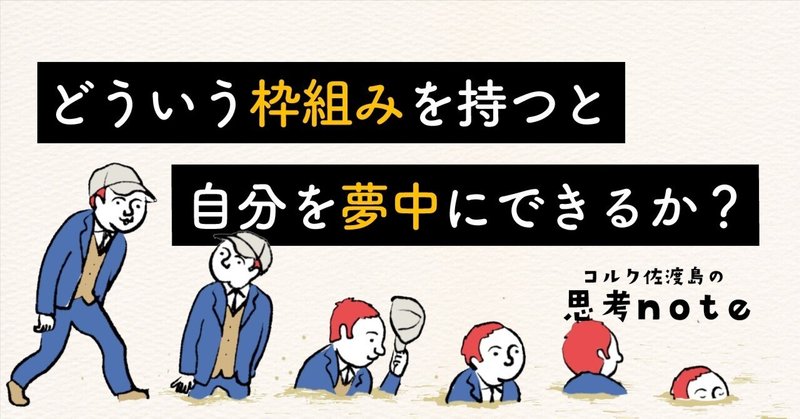佐渡島庸平(コルク代表)
記事一覧
もし遺書を書くなら、そこに何を書き記す?
自分は次の世代に何を「引き継ぎ」たいのか。
先月『贈与の存在に気づき、次の代に引き継いでいく』というnoteを投稿したが、40歳を超えて人生の折り返し地点が見えはじめた辺りから、この問いについて深く考えるようになった。
そんな中、自分の人生観について、気づきを与えてくれる出来事があった。
ぼくのnoteで何度か紹介しているが、5年ほど前から『EO(Entrepreneur’s Organiz
“Common”となるコンテンツを、どう生み出していくか
オリジナリティとは何なのか?
これまでの時代、他の人が絶対にマネできない卓越したクオリティを届けることが一流と呼ばれてきた。他の人がマネできないからこそ、そこにオリジナリティがあると見なされてきた。
だが現在は、多くの人が簡単にマネができ、みんなが楽しめるネタを提供する人が親しみを持たれ、人気者になる。
Instagramでは、インスタ映えする投稿を続けるだけでは、フォロワーを増えない。料理
「変化の激しい時代」という言葉への違和感
思考は言葉でできている。だから、思考を深めるためにできることは、一つだけ。言葉を精査することだ。
以前に『思考停止を促す言葉を使わない』というnoteを書いたが、世の中には、意識せずに使うと思考停止を促す言葉が幾つかある。ぼくのnoteでは、そうした言葉たちについて何度か紹介してきた。
例えば、「頑張る」や「覚悟を決める」は、そうした言葉の代表格だ。
これらの言葉は、精神的興奮で課題克服を図
絶対と見えて“不確か”な、概念の囚われに気づく
仏教には「色即是空」という言葉がある。
すべての形あるもの、物質的なものは、その本質においてはどれも実体がなく、「空(くう)」であること。それゆえ、なにものにも執着する必要はないという考えだ。
この世の物事は全てが移ろう。だから「絶対」など存在しない。現在ここに確実に存在しているように思える「私」でさえ、絶対ではない。様々な物事との関係によって、そう感じられているだけだ。
すべての物事は常に
編集者としての気概を、問いただされた作品
世の中のあらゆるところで「エンタメ化」が進んでいる。
エンタメにおいて重要なのは没入感だ。派手な演出や巧妙な伏線を駆使し、続きを知りたいという期待感を高めることで、観客の目をコンテンツから離れないようにする。
そして、没入感を高めるために欠かせないのが「わかりやすさ」だ。複雑な設定や展開は、観客を混乱させてしまう。シンプルで直感的な表現を用いることで、観客は瞬時に物語に入り込み、感情移入しやす
物語を語ることによって、自分の経験を客観化する
ぼくにとって、読書とは「作者との対話」だ。
「なぜこの一文を書いたんだろう?」「あえてこの言葉を選んだのはどういう理由だろう?」と考えながら、一文一文を読んでいると、頭のなかで作者と会話してるような気分になる。
ぼくは、作者が書いている内容に共感してではなく、それを書こうとしている作者の姿勢や生き方に共感して、その作者を好きになるのだろう。
村上春樹の『風の歌を聴け』の冒頭に、こんな文章があ
贈与の存在に気づき、次の代に引き継いでいく
数年前から、「引き継ぐ」という言葉について、よく考えるようになった。
ぼくらの日常は色んな人からの贈与の積み重ねで成り立っている。それは、現代を生きる人たちだけでなく、過去に生きた人たちも含めてだ。
『世界は贈与でできている』という本では、自分の知らない誰かが社会の安定性を維持していることに注目し、その誰かのことを「アンサング・ヒーロー」と呼んでいる。
歌われなかった英雄たちが、この世界の日
“情報“として伝えるのと、“物語“として伝わるの違い
「物語の力で、一人一人の世界を変える」
このミッションをコルクでは掲げているが、最近、「物語の力」について改めて再認識している。
以前に『見えないものに気づく、大胆なポジションチェンジ』というnoteでも紹介したが、ぼくがAIを使って作成したマンガを、マンガ家の羽賀翔一君に添削してもらう企画をYouTubeではじめた。
マンガを描きはじめたばかりの人や、マンガを描くことに興味がある人。そうし
固定化された“知”ではなく、動的な“知”をどう学ぶか?
現在、長男の不登校が続いている。
少し前に投稿した『子どもに“委ねる“覚悟と、子離れの難しさについて』というnoteにも書いたけど、去年の1学期までは学校に通っていたが、2学期の途中から途端に行かなくなった。
この春で中学2年生になったのだけど、新学期が始まってからは一度も学校に行っていない。それどころか、欠席や遅刻の連絡すら学校に入れていない。まるで学校が存在していないかのように、堂々と学校
作家性を損なわずに、作品を世界に届けるには?
昨年、中国へ出張した時に感じたことを、『復讐もの以外描けない。この現実について思うこと』というnoteに投稿した。
この10年近くで、中国のマンガ市場はとんでもない規模に成長している。基本的にアプリでマンガは読まれていて、人気を占めるのは「国漫(グォーマン)」と呼ばれる国産マンガだ。そして、そのほぼ全ては「フルカラー・縦スクロール」で描かれている。
この中国出張では、マンガ制作に関わる色々な人
本当の理解とは、「分けて考える」の先にある
ぼくは昔から食べることが好きで、大学生時代はアルバイトで貯めたお金で、一流と呼ばれるレストランに足を運ぶことが趣味だった。
一流の料理人がつくる料理は、ただ美味しいだけではない。
そこには料理人の魂みたいなものが息づいていて、その人の哲学が凝縮されているように感じる。それは世界観といってもいいかもしれない。そういう料理を食べ終わると、いい作品を読み終わった後のような気持ちになる。
ぼくが思う
臆せず挑戦に踏み出せる『なあんだの法則』
「人は、人によって磨かれる。」
人はひとりで勝手に育っていくものではない。人は、人に揉まれて、磨かれ、育っていく。
だから、人が成長していくために重要なのは、本人の覚悟や意思の強さではなく、仲間と切磋琢磨しあえる「環境」だと、ぼくは考えている。
ドラゴン桜では、『なあんだの法則』というものが登場する。
なぜ東大に合格するのは、進学校の生徒が多いのか?。この質問に対して、「進学校には、そもそ
まきこまれ上手こそが、人生をより楽しめる
新しい視点を得るために、普段とは違うポジションの経験は重要だ。
そうした話を、先日『見えないものに気づく、大胆なポジションチェンジ』というnoteに投稿した。
物事を見る枠組み(フレーム)を変え、違う視点で捉え、新しい発見や学びを得る。そうすることで、得られるインプットの量と質が変わり、価値基準が磨かれることで、アウトプットに大きな変化が生まれる。
いかに視点を固定化せずに、枠組みに揺さぶり
他者の足跡を追うことで、自分は何者かを知る
「成長し続けることが重要」という考えは、一般的なものにみえる。だが、人生において大切なのは、成長よりも「成熟」だと考えている。
ぼくが考える成熟とは、社会が求める基準を手放し、自分なりの基準を手にいれ、それを楽しみながら追求することだ。
成長は数値で測ることができるが、成熟は数値で測る事ができない。成長は一方向に加算的に進むものだが、成熟は多方向に広がり、時に矛盾を抱えるものだ。成熟とは、その
どういう“枠組み”を持つと、自分を夢中にできるか?
“今後……二度と「頑張る」とは言わない。
「全力」「がむしゃら」「必死」。これらの言葉も今後使わない。”
『ドラゴン桜2』で、桜木は生徒たちに向かって、「頑張る」という言葉を口にすることを禁じる。
「頑張る」は精神的興奮で課題克服を図ろうとする勢いだけの感嘆符でしかない。「頑張る」という言葉は使わずに、「なんのために、何をするか」を考えて、機能的に話すことを習慣にしようと、桜木は言う。
自分